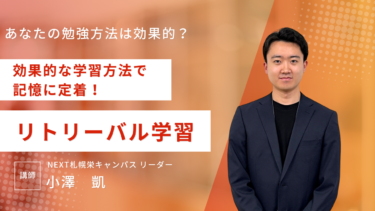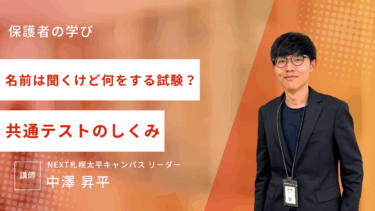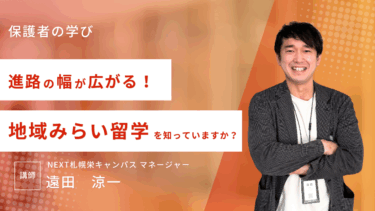こんにちは、NEXT札苗キャンパスです。
年度初めに実施した学年別ガイダンスでは、学習法だけでなく、スマホとの付き合い方についても、生徒のみなさんにお伝えしました。
今回のブログではその内容を共有しながら、保護者の皆さまにこそ知っていただきたい「スマホ管理のポイント」や「スクリーンタイムの設定方法」についてご紹介します。
スマホが脳を壊す?
ガイダンスでは、生徒たちに問いかけました。
「勉強中、スマホはどこにありますか?」
通知が鳴るたびに見てしまう
→ 気づけばLINE、YouTube、SNS……
→ 結果、集中できず、勉強した“つもり”だけが残る
これはよく言う「ながら勉強」というもので、学習の効果を大幅に下げてしまいます。
実際に、
- スマホが同じ空間にあるだけで3時間勉強しても学習効果はたった30分の勉強と同じになる
- スマホの使用が3時間を超えるグループでは、偏差値50を超える人がほぼいない
- 睡眠時間が5時間未満では、3時間以上勉強していても成果が出にくい
というデータも示されました。
生徒たちには「どうスマホを使うかは、自分の意志でコントロールできる」と伝えています。
ですが、中高生に“意志の力”だけでのコントロールを求めるのは難しい時期でもあります。
そこで私たち大人の出番です。
スマホの使い方、親ができるサポートとは?
スマホには、時間管理や使用制限を行う機能が備わっています。
ここでは、iPhoneの「スクリーンタイム」設定を例にご紹介します。
【スクリーンタイムの基本設定(iPhoneの場合)】
- 「設定」アプリを開く
- 「スクリーンタイム」→「スクリーンタイムをオンにする」
- 「これは自分用です」→「親用に設定」を選択
- 使用可能時間(例:1日2時間)、休止時間(例:22:00~翌6:00)を設定
- 「スクリーンタイム・パスコード」を設定(お子さんに知られないように!)
【制限できる内容】
- アプリの使用時間(ゲーム・YouTubeなど)をカテゴリごとに制限
- 特定のアプリを使用できない時間帯の設定
- 有害コンテンツや購入の制限
Androidでも「Digital Wellbeing」や「ファミリーリンク」など、似た機能が使えます。
信じる+見守る=安心のスマホ利用
子どもの「やる気」や「自律性」を大切にしたいというお考えは大変素敵です。
ただ、「環境」や「仕組み」で支えることも、成長の手助けになるということを忘れてはいけません。
スマホを完全に禁止するのではなく、“使い方”を親子で一緒に考えることが、これからの時代に必要なスタンスです。
ガイダンスでお伝えした内容は、保護者の皆さんとも共有したいことばかり。
ぜひご家庭でも、お子さんと「スマホの使い方」について話す時間を持ってみてくださいね。
【参考文献】「スマホがどこまで脳を壊すか」(榊浩平 著)
ガイダンスは以下のリンクからご覧ください!
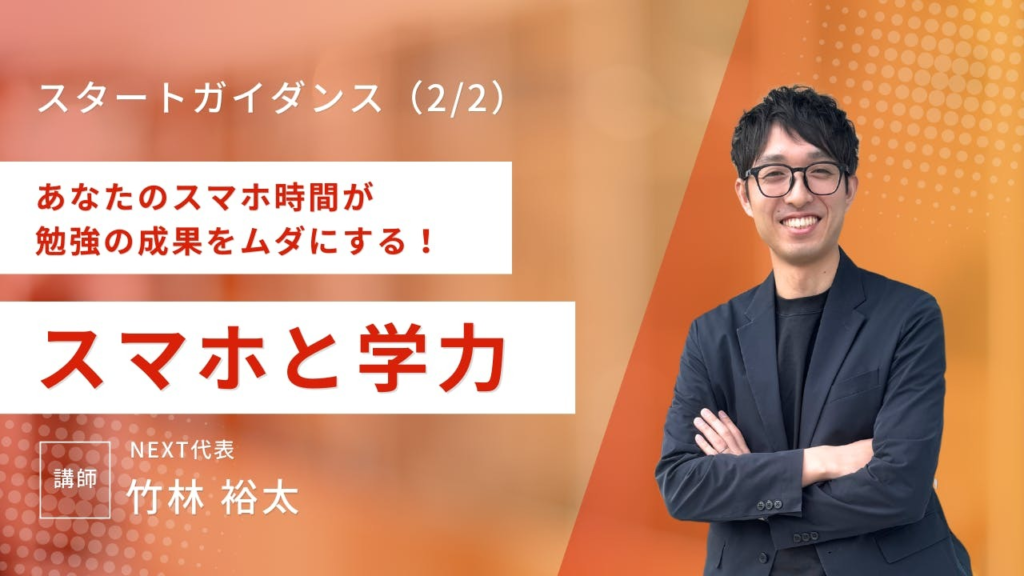
それでは、また次回の記事でお会いしましょう!