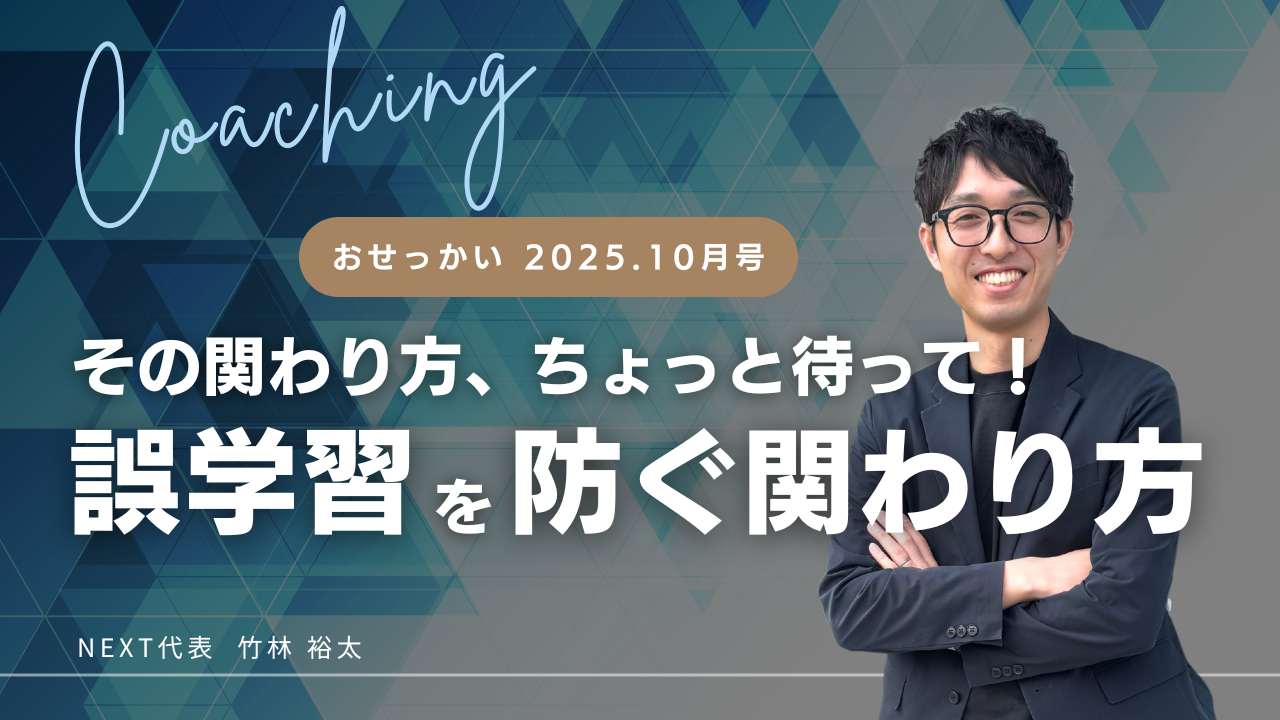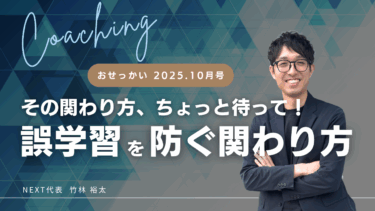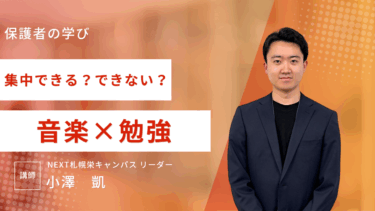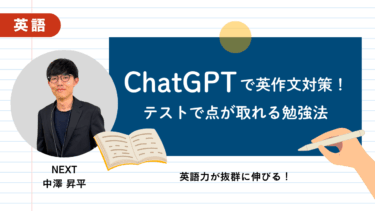NEXT代表の竹林です。
私は3児の父で、みなさんと同じように、子育ての悩みを抱えながら日々を送っています。
子育てって、楽しいこと、幸せなこともたくさんある反面、経済的・身体的・精神的な負担感もありますよね。
特に、子どもたちとの関わり方…どんな関わりがよいのだろう?と教員目線の方法論以外にも、家庭ではどう関わればよいのだろう?と今年はいろんな本を読み漁っています。
そこで今日は、その中からみなさんにご紹介したい「誤学習」というテーマについてご紹介したいと思います。
誤学習とは?
誤学習とは、本来なら身につけるべきでない行動を、メリットのある行動として誤って学習してしまうことをいいます。
例えば、
- 癇癪(かんしゃく)を起こせば、要求が通る
- できないフリをすれば、手伝ってもらえる/免除される
- いい子でいれば褒められるので、自分の本音は言わない方がいい
などの行動です。わが子が駄々をこねている姿は、親からすればすぐに解決したいですよね。また、我が子にはいい子でいてほしい。その気持ちもよくわかります。しかし、親である私たちに本音を言えずにいるのも、親としては悲しい気持ちになります。
では、私たちはどのように子どもたちと関わっていくべきなのでしょうか?
判断基準は10年後その子のためになるかどうか
誤学習が起こる原因は、私たちの過度な譲歩にあります。
例えば、学校が面倒だから行きたくない。と言われたときに、どう捉えるか?です。
もちろん、学校でトラブルを抱えていたり、言いにくい悩みがあるのかもしれません。ですから、そこに「そんなのはありえない!」と感情的に対応するのも間違っています。
最後までわが子の味方をしてあげられるのは、私たち親だけです。
ただし、いろいろと話を聞いてみて、怠惰が原因だったり、気持ちが疲れているだけかもしれません。
大切なのは、そこで譲歩するときに、10年後その子のためになるかどうかという判断基準です。
もしそれが、あまりその子のためにならないということであれば、譲歩の仕方を考えなければなりません。そこで役立つのが120%の法則です。
120%の法則
120%の法則とは、子どもの提案に対して120%に妥協点を置くことです。例えば、毎日10問勉強する約束をしているとして、今日はやりたくないと言い出してきたとします。
頑張ってやってほしいあなたが粘ると、じゃあ5問は?などと交渉になることがあります。
この交渉がそもそも間違い。だって、10問するというのが約束ですから。
でも、その子のために、今日は妥協したほうがよいというときもあるでしょう。(繰り返しますが、10年後その子のためにならないのであれば、約束ごとですから、そもそも交渉のテーブルにつく必要もありません。)そのときは、相手の提案の120%、今回で言えば6問に妥協点を置くのです。
そうして、じゃあ6問はやろう!それ以上は譲れないよ!と伝えるのです。
こうすることによって、主導権が保護者にあることを学びます。5問でいいよ!と伝えると、子どもは主導権が自分にあることを学ぶのです。
人生の主導権は本人にあるが…
人生の主導権は子ども自身にあります。ですが、本人に任せるばかりでは、やりたいことにばかりエネルギーが注がれてしまい、やるべきことがおろそかになってしまいます。だからここでは保護者の関与が重要なのです。
わが子の発達の段階ではわからないテーマにだけ主導権を持ち、少しずつ発達状況に合わせて子どもに主導権を渡していく関わりが重要です。いつまでも子のすべてに主導権を持ち、子は保護者の言いなりになるものだという感覚を持っていると、子どもは何でも親の顔色をうかがって行動するようになってしまいます。それもまた、誤学習です。
あくまでも発達に合わせてです。年齢ではありません。年齢的にできていてほしいことでも、まだ一人でできないものについては関わるべきです。(このさじ加減が難しいですが…)
最終的には、自立して自分でできるようになってもらわなければいけません。私たちの優しさが、間違って子どもたちに伝わってしまうことのないように、関わりを見直してみましょう。