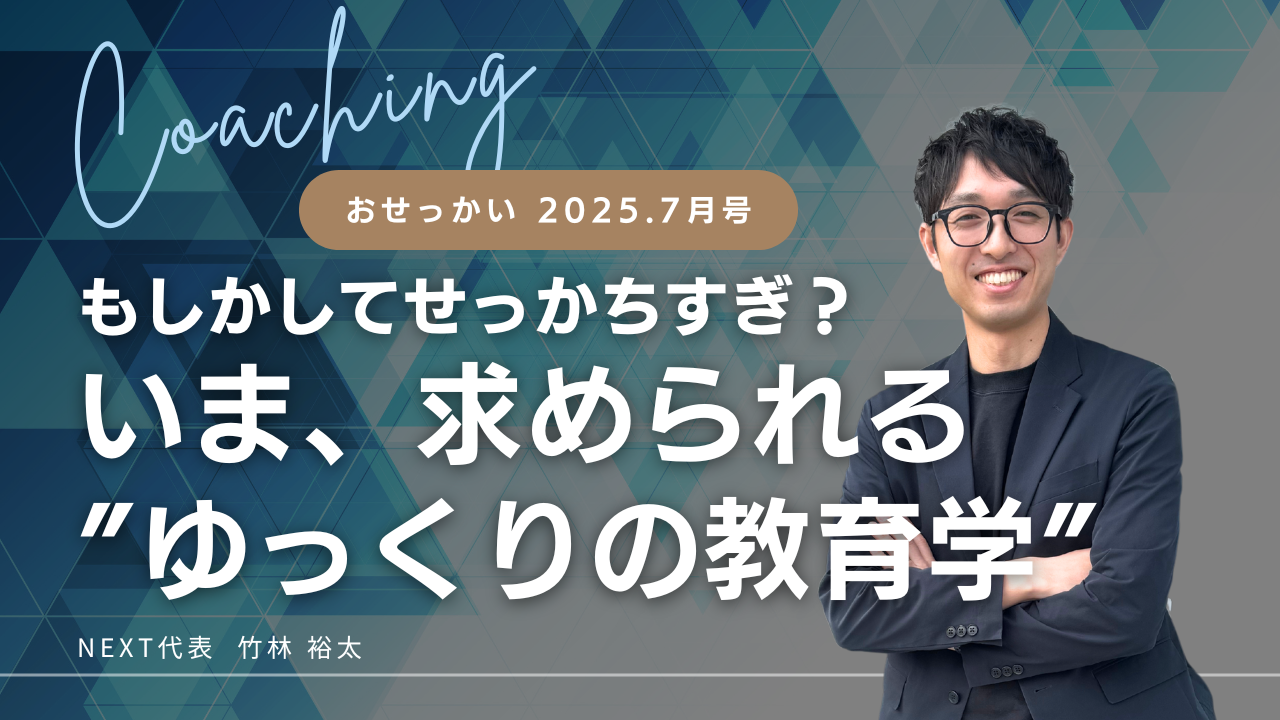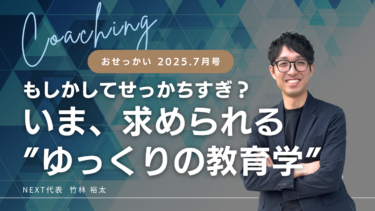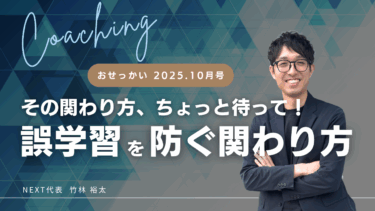今年のGWに、大阪・関西万博に行ってきました。
行くまでの間、私はいろいろな国のことを子どもたちといっしょに調べたり、今回の万博のテーマである「いのち」について展示するパビリオンのことを調べたりしていました。
調べる中で特に興味が湧いたのが福岡伸一さんが手掛ける「いのち動的平衡館」のメインテーマである「動的平衡」という考えです。
今回「動的平衡」についての説明は、他に譲ることにしますが、福岡さんの本の中で紹介されていたある科学的発見に関するエピソードに、子育て中の私はハッとさせられました。今日はそのエピソードをご紹介します。
ES細胞を見つけた人のはなし
2007年のノーベル賞を受賞した、マーティン・エヴァンズさんは、ES細胞を発見した人物です。ES細胞は受精卵を元に作られ、体内のあらゆる種類の細胞に分化できます。ざっくりいうと、組織や臓器を人工的につくり、これまで治療できなかった病気が治療できるようになるかもしれない!という発見です。山中伸弥教授が発見したiPS細胞の研究にも大きく影響を与えた研究として知られています。(ちなみにES細胞は受精卵をベースにして作られるため倫理的問題が課題ですが、iPS細胞は皮膚細胞からつくることができるため倫理的な問題がないため実用性に期待がかかっています。)
福岡さんの「生物と無生物のあいだ」という本の中では、このエヴァンズさんがES細胞を発見する過程が詳細に記述されています。エヴァンズさんは、時間をかけてマウスの細胞を観察する中で特異な腫瘍に出会います。この腫瘍から、どの細胞・組織になるのかが決まっていない状態(=未分化)の細胞を見つけることに成功しました。しかし、それだけではたまたま特殊な細胞を見つけただけ。科学には再現性が求められます。
そこで、エヴァンズさんは、未分化の細胞のメカニズムを解明するため、地道な観察を続けます。
当時はそれが「何になるのか」分からない手探りの状態だったにも関わらず、彼は時間をかけて実験を繰り返す中で、未分化な細胞を、試験管の中で「維持しつづける」条件を探ることに成功したのです。彼は「特別な技術」や「大きな装置」なしに、ごく普通の顕微鏡とピペットを使い、何年も観察を続けることでノーベル賞を勝ち取ります。
当時の科学界では、「新しい技術」や「斬新な操作」によってデータを生み出すことが、評価されていたそうです。手段の高度さ=研究の価値というような風潮の中で、エヴァンズさんのような地道に時間をかけるやり方は時代遅れとされ、周囲の研究者はそれを蔑むような態度だったそうです。しかし、そんな最新・主流を標する科学者たちの方法では、ES細胞を発見することはできず、彼の地道な時間をかけた方法が成果をあげたのです。
せっかちに結果を求めていたら…
私たちは、早く結果を出すことがよいことと考えがちです。我が子にも、そう接してしまうことが多いのではないでしょうか?
私がこのエピソードを知って深く反省したのは、子どもが時間をかけていること=よくないこととして捉えてしまっていた点です。私も、じっくり作図している我が子を見て、もっとさくっとできないかな〜とか、もっと短い時間でたくさんの問題を解いてよ!とよく思ってしまい、実際に急かすような声掛けもしてしまうことがあります。
でも、もし私が結果を急いでせかしてばかりいたら、私の生徒にエヴァンズさんのような結果を出す人は出てこないかもしれません。つい、急いで結果を求めてしまいがちですが、以前の記事でもご紹介したように長期的な成果に着目した関わりを大切にしなければ、子どもたちが継続すること、深く理解することの大切さ、こだわることを知らない大人になってしまうかもしれません。
スロー・ペタゴジー
近年、スロー・ペタゴジーという考え方が広まりつつあります。「ゆっくりの教育学」を意味する言葉で、ゆっくりと、深く、時間をかけて学ぶことを重視する教育の考え方です。
つい、ゆっくり=悪ととらえてしまいがちですが、このエピソードはゆっくりの価値を教えてくれるよい教材だと思います。もちろん、短い時間で成果を出す考えも大事です。ですが、ついつい忘れてしまいがちだからこそ、「ゆっくり」にも目を向けたいですよね。
親である私たちも、子どもたちが課題に継続して、じっくり向き合うことを応援できる余裕を持ちたいものです。