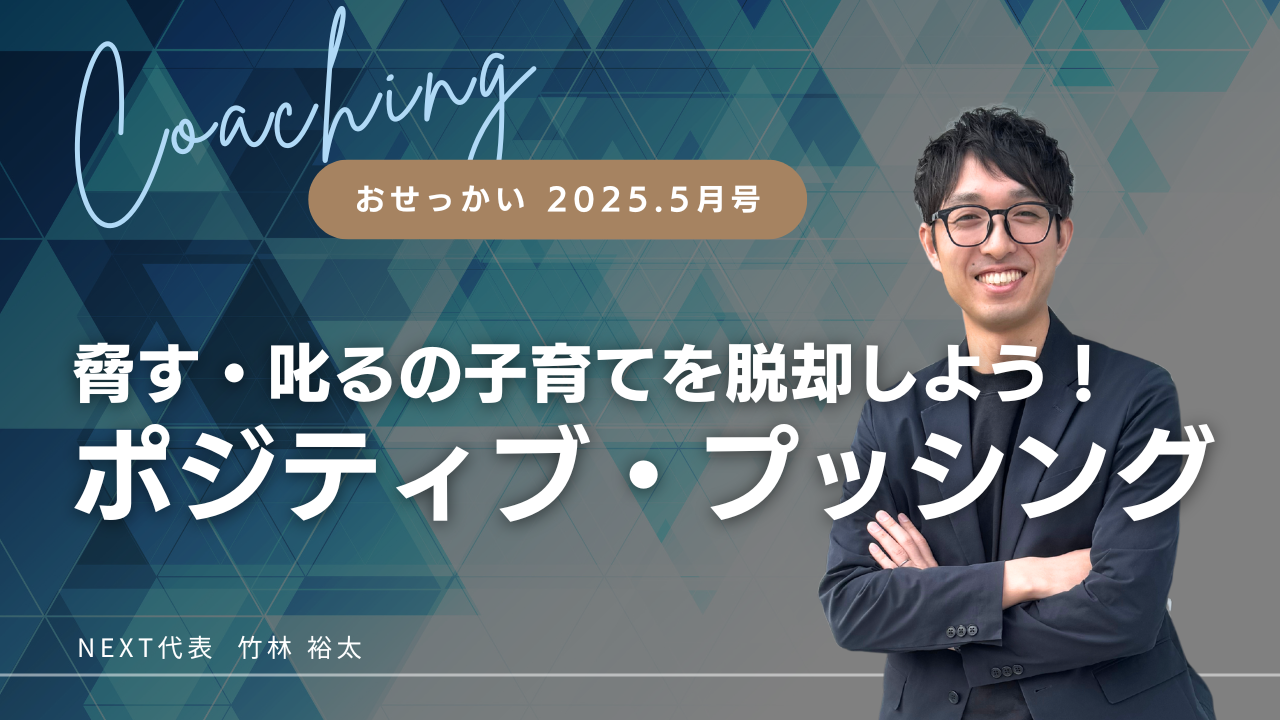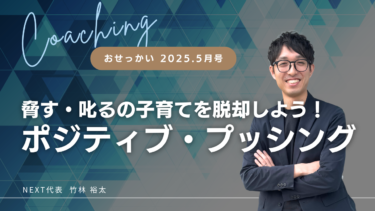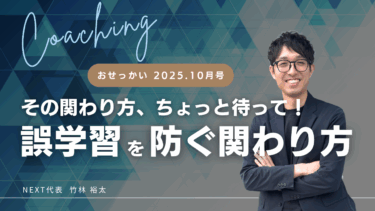多くの人が「人の育て方」を学ばない
みなさんは、いま話題の教育書『エビデンスで子育て』(中室牧子著)という書籍をご存知でしょうか?前書である『学力の経済学』もベストセラーとなり、続編として気になっていたので、先日読ませていただきました。
その中の前書きを一部抜粋してご紹介します。
私たちのほとんどが、人生のどこかで「人を育てる」役割を担います。時に親として、教員として、指導者として、上司として、先輩として、誰かを育てていかなければなりません。それにもかかわらず、人を育てるための効果的な方法や技術を学ぶ機会は多くありません。本書はデータや経済学、それが生み出すエビデンスの力を使って、「人を育てる」あなたを助けます。
ー『エビデンスで子育て』(中室牧子著)より抜粋
この前書きがすべてを語っているように、私達はよくわからないまま、自分が経験した方法で子育てや部下・後輩育成をしてしまうことが多いように思います。
もちろん、教育の分野にも様々な知見があるものの、自ら学ぶという機会はそう多くなく、自分がやってみて・受けてみてよかったからという経験則によるところが大きいのではないでしょうか?
私たちはここに着目し、NEXTを保護者の皆様に子育ての学びや気付きを得ていだだける機会を提供しようと取り組んでいるところです。
教育は短期的成果よりも長期的成果が重要
私も三児の父ですが、気をつけないとついついテストや通知表の結果といった短期的な成果ばかりに注目してしまいます。しかしながら、この書籍はそうした短期的成果よりも、長期的な成果に着目すべきだと警鐘を鳴らしています。
この書籍では、認知能力(テストや検査で測れる能力)よりも、テストや検査では測ることのできない物事に対する考え方、取り組む姿勢、行動力などの非認知能力こそが将来の年収や学歴に大きく影響すると紹介しています。
※ちなみに企業に対して、新入社員に求める能力を調べたところ、非認知能力を指す回答が上位を独占しています。とはいえもちろん、企業の多くが採用時に適性検査やWEBテスト等で認知能力もチェックしていますから、認知能力がどうでもいいとはいえません。ですが、その認知能力の伸びすら非認知能力の影響を強く受けるそうです。
では、長期的成果に着目したわが子との関わり方とはどのようなものなのでしょうか?
ポジティブ・プッシング
スポーツ心理学者で、子育てのエキスパートとして知られるジム・テイラー博士は、子どもと関わる際に子どもがこの8つの感覚を持てるように導いていく、ポジティブ・プッシングという関わり方を提唱しています。
この8つの感覚を大人になるまでに獲得していくことで、受験や人生の課題に対して過度にストレスを感じることなく、乗り越えていく力がつくとされています。
第1条 わたしは愛されている(自己信愛感)
第2条 わたしはできる(自己効力感)
第3条 大事なのは挑戦すること(チャレンジ精神)
第4条 自分の行いに責任を持つ(自己責任感)
第5条 失敗しても大丈夫(失敗受容感)
第6条 間違っても修正できる(逆境対処能力)
第7条 自分のやっていることが楽しい(自己幸福感)
第8条 わたしは変わることができる(自己変容感)
親であれば誰でも、子どもの点数の悪いテストを見たとき、子どもが言う事を聞かないとき、感情のまま叱ってしまったり、子どもたちの尊厳や自信を傷つけてしまうような、あとでしまった!と反省する関わりをしてしまった経験があるのではないかと思います。
このポジティブ・プッシングは、長期的な視野に立った子どもたちとのよい関わり方を教えてくれます。感情的な関わりも、もちろん子どもたちの幸せを願っているからこそのものですが、それでは8つの感情・感覚を子どもたちに感じてもらうことは難しそうです。
特に、成績が思わしくない子どもたちの多くは、「自分ならできる」「挑戦することが大事」といった、これらの感覚は自分では持りにくい状況にあります。認められるチャンスが足りないのです。子どもたちが自分の力で状況を打開できるようになるためにも、彼らの持っている力や可能性に気づかせてあげる関わりが大切です。
特に、叱るという行為は気をつけなければなりません。
叱るときのコツは
・人格ではなく行動にフォーカスする(〜が良くなかったと思うよ)
・具体的な理由を添える(〜したから困ったよ)
・代替案を提示する(〜してみたらどうかな?)
・次どうしようと思うのか自分の口で語ってもらう(次はどうしようと思う?)
ことです。
日々のわたしたちの関わりが、子どもたちの自信につながります。子どもたちの「できる!」という感覚こそが、成長のエネルギーになるのです。
成果を出すためには、一見遠回りにも感じられるような長期的な視点に立った関わりが大切です。日々の学びの成果を大きくするためにも、関わるみんなで子どもたちとの関わりを再考したいものです。